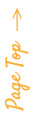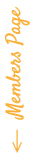たなばた
今年も、先週の教室の時間に七夕飾りをし
ました。5色の短冊に筆で思い思いの願い
を書いて七夕竹に飾り、楽しんでもらい
ました。
七夕は本来、陰暦7月6日の夜から翌朝にか
けての行事。今でも地方によっては8月に
行うところも多くありますし、もっとも、
そちらのほうがお天気がいいから、牽牛と
織姫の星合を見られるというもの。
やはり、日本の暮らしは陰暦を知ることで
理解できることが多くあります。
そのような七夕も、古くは奈良時代に中国
から伝わる乞巧奠につながり、万葉集にも
多く詠まれています。
また、江戸時代では、6日の朝に里芋の葉
の上に溜まった露を集めて墨を擦り、短冊
に筆の上達を願う風習があったそう。
七夕に、筆の上達を願う。
教室でも、字がきれいに書けるようにとか、
書が上達するようにと、いくつもの短冊に
書いてありました。短冊を前に、子どもか
ら大人が、自己に願いを問う姿、わずかな
時間でも、それぞれの思いを墨と筆で書き、
七夕竹に飾るその瞬間の尊さを思います。
そして、いにしえの人々が四季折々の日本
の行事に込めた思い、その美しさをも感じ
ることで、生活の知恵もよりいっそう深ま
るのではないでしょうか。