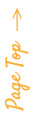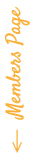くまの
書のなかで、もっとも日本の美意識を感じるの
が平安時代から鎌倉時代はじめにかけての古筆。
流れるような連綿、豊かな散らしがき、美しい
料紙など、この時代特有のみどころ多い書です。
洗練された国風文化が発達した平安時代ですが、
法皇や上皇の熊野御幸がはじまったのもこの頃。
江戸時代には多くの人々が目指した熊野の地。
そんな熊野参詣へ春彼岸に行ってきました。
熊野三山が多くの信仰をあつめたのには、熊野
権現の神仏一体、貴賎、老若男女など、わけ隔
てなく、なんびとをも受け入れる懐の深さにあ
ったようです。
公共交通機関が発達している今とは違い、当時
は険しい山路を命がけで、ただひたすら歩いた
覚悟はいかばかりだったかと想像します。
いにしえの人々の心を掻き立てた熊野三山です
が、今は欧米人に圧倒的な人気があるのだそう
で、たくさんの外国人観光客に出会いました。
神社での参拝姿、平安装束体験で、当時の巡礼
や旅の装束を着て楽しんでおられる姿をみかけ、
熊野の地がこんなにも賑わいをみせているとは
思いもよらず新鮮でした。
日本人があたりまえだとしている文化や慣習に、
外国人観光客はとっても感動するそうですし、
日本の伝統文化への関心も高いとは知っていま
したが、それをもとめる人が以前より増えてい
ることを目のあたりにした熊野参詣でした。
そのなかで書道も大人気なのです!