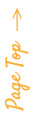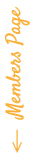冬の夜
12月、一年の終わり。
照葉は一葉一葉と舞い落ち、自然は冬枯れへ
と景色を変え始めました。それと対応する街
の賑わいに、一抹の寂しさを感じます。
木々の葉が落ちる、遠くから落ちてくるように、
空のかなたで庭の木立が枯れているのか、
木々の葉は、拒む身ぶりで落ちてくる。
そして夜には重い大地も ほかの星たちから
離れて、孤独のなかへ落ちてゆく。
わたしたち、みんな落ちる。この手も落ちる。
ほかの人たちを見てごらん。
落下はすべての人にある。
けれども、この落下を限りなくやさしく
両の手で支えてくれる存在がある。
『秋』
リルケ詩集 神品芳夫:編訳
リルケは、日本の俳句に興味をもち、
「短い驚き」と表現し、自らも三行詩など
の短い詩を好んで書いていたようですが、
地上や大地がしばしば用いられる詩は、
人間の存在の意味を深く思索しています。
子どものころ、リルケの詩に惹かれたのは
なぜだろうと、あらためて読んでいます。
静かで長い冬の夜、炬燵にもぐり、読書を
するのも気分が落ちつくというもの。
気忙しくなる月だからこそ、今ひとたび
立ち止まることは、かぎりなく意味がある
ことのように思います。
地上にあるものが君のことを忘れていたら、
静かな大地に向かって言うがいい、
私は流れると。
速い水の流れに対しては言うがいい、
私は留まると。
『オルフェスへのソネット 二十九』
リルケ詩集 神品芳夫:編訳